 想いを知ったら力になりたい。
想いを知ったら力になりたい。
−−茶屋さんは、森本さんたちの想いに感銘を受けたことで、イヌワシストアを通して一緒に取り組むということになったそうですが、改めてキッカケについて教えていただけますか?
茶屋さん:そうですね、今回一緒にやらせていただいた理由は、自然環境保全への強い目的意識や使命感というより、素直に森本さんたちの強い想いを感じて、サポートしたいと思ったのがキッカケでした。
もちろん地域の自然を守っていきたいという意識はありますが、それが大きな理由となっているのではなく、僕は”誰がどんな想いで取り組んでいて、それに対して自分は何ができるのか”ということを大事にしています。
そして、その信頼できる人が少しでも喜んで、「幸せになってくれたらいいな」と思えたとき、自分が一緒に“やる理由”につながっていってると思っています。
今回は、森本さんや他の担当者の方々がイヌワシや自然保護の観点で、木を伐採していて、その木材をいろんな形で活用したいというお話でした。
皆さんの真剣さを受けて、今の自分の仕事の中で僕には何ができるかを考えました。そこで思ったのは、一緒に木を伐ったり、最前線で啓蒙活動の旗を振るとことはできないけど、カフェ(イヌワシストア)で過ごした人が、イヌワシのことや地域の自然について知るキッカケを作ることはできるのではないかと思いました。

−−なるほど!イヌワシストアに私もお邪魔して感じたことがありましたが、今のお話で繋がりました!
『イヌワシ』って店名にもなってるくらいコンセプトもしっかり提示しているけど、イヌワシを守りたいとか、自然保護運動をしている人たちが集い、濃い情報がインプットできる場ではなく、たまたま行ったカフェで、イヌワシを守ろうという、ちょうどいい情報量にさりげなく触れることができる場という印象を持ちました。
そして、店内にはイヌワシストアのロゴを使ったグッズなどもありましたが、もしかするとイヌワシを守りたいからという動機ではなく、オシャレでかわいいから購入する人も多いのかなと思います。
茶屋さん:そうなんです。僕たちの役割が、キッカケを作ることなら、そのさりげない情報量くらいがちょうどいいと思っています。グッズもそのキッカケの一つのコンテンツだと思っています。
そうやってカフェで“イヌワシ”のことを知って興味を持ったとしたら、あとはその人が自ら調べて、ニュースや専門的なところで情報を取りに行くはずなので、僕らはキッカケづくりという立場で啓蒙できたらと思っているんですよね。
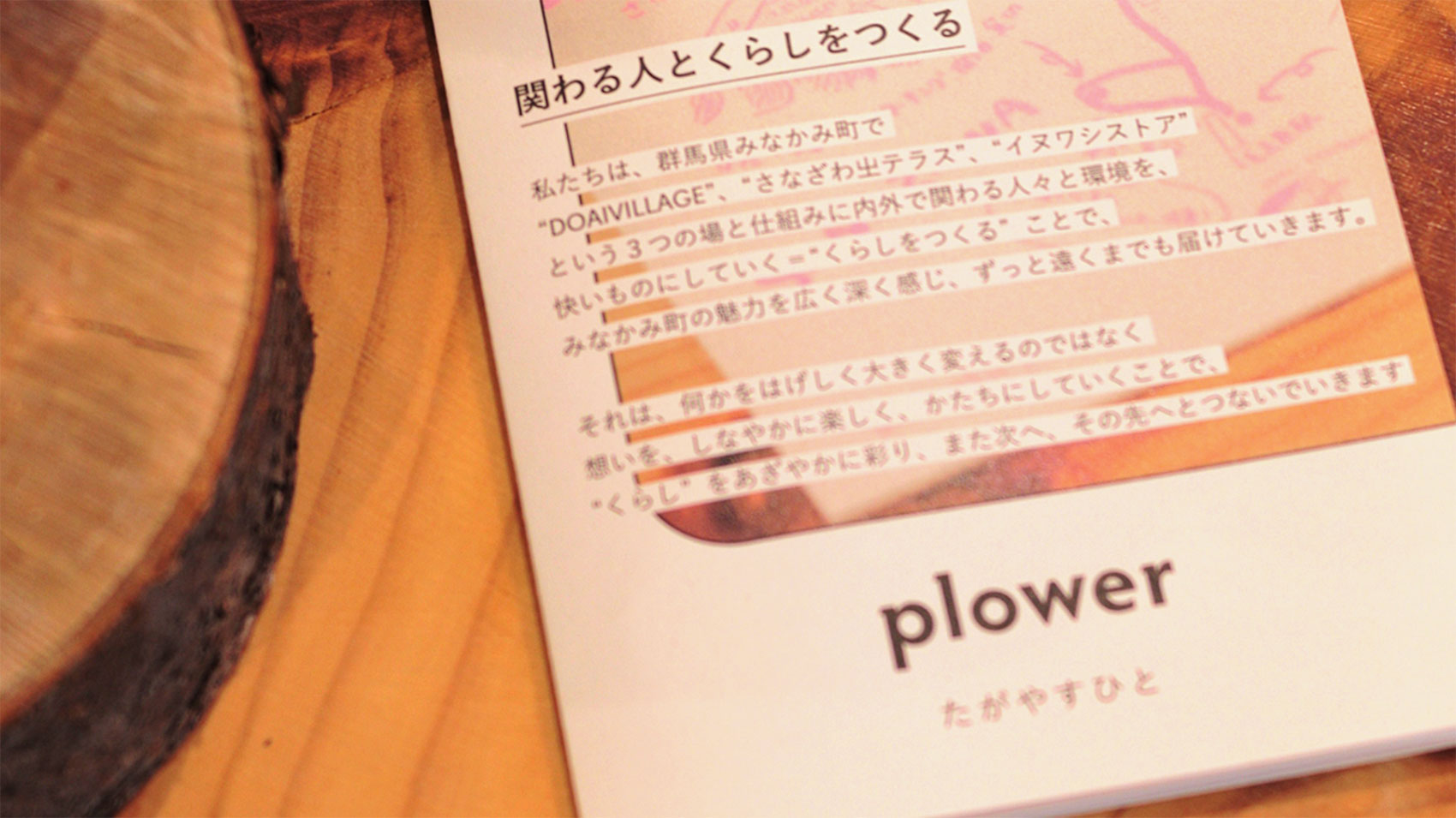
「つなぐ役割」として、できるだけのことを
森本さん:今のお話しを伺っていて、すごく嬉しくなりました!本当に伝えていくのは難しいんです。林野庁は国の組織ですし、私たちも当事者として間違いなく伝えなければいけないので如何に正確に伝えるかというプレッシャーも正直あります。
例えば、「生物多様性の復元」とか一般の方にしてみたら意味がわからない言葉でも、先人たちが使ってきた言葉を常に使い続けたいという考えがあって、それを勝手に言い換えるということは結構な覚悟と責任を背負うことになるんですよね。
だから、少し難しい印象を与えてしまうこともあって、うまく伝わっていないところもあったんだと思います。でもそこを茶屋さんは、赤谷プロジェクトのメンバーとしてではないので、アプローチの方法には自由度があるわけです。
地域の事業者が、その方々のそれぞれ自分なりの解釈で赤谷プロジェクトを語り、知ってもらう“キッカケ”をつくるっていうのが、新しいやり方だと思います。だからこそ色々とまだできることもあるのかなって可能性を感じていますね。

茶屋さん:そうですね。「赤谷プロジェクト」のメンバーではない僕らだからこそ自由に伝えることができるのであれば、僕らなりのアプローチをしていくことは継続していきたいですよね。また、これから先に作られていく歴史の中で、いろんなステークホルダーと意見や価値観が異なって、時には対立することもあるかもしれません。
でも、そうやってコミュニケーションをとっていく中で、いろいろな意見をお互いぶつけ合って、そこから生まれる“摩擦”によって、この取り組み自体に新たな熱が生まれるからこそポジティブな変化が起きると僕は思います。
先ほど、森を作るのに時間がかかるというお話しがありました。人はつい「自分が生きてるうちに」「元気なうちに」何か経済的にも精神的にもリターンがほしいって思っちゃう生き物だと思うんです。でも、実際にはそんなに簡単に手応えなんて得られない。今自分は本当に森づくりの中の“ごく一部”にしか関われてないんだなって思っていますが、そんな中で「つなぐ役割」としてできるだけのことをやっていきたいですね。
森本さん:頼りにしています!いろいろな考えがある中で、いろんな人がそれぞれの解釈をすることもあると思います。ただ、それらの核となる想いのところは変わらずに、解釈する人によってちょっと変化しながら伝わっていくっていうのは、それはそれで、すごく自然で健全なことだと思いますね!

厳しいコスト面。共感を得ながら持続可能な取り組みへ
イヌワシの狩り場をつくるために、森の一部を伐採する。そんな取り組みの中から生まれたのが「イヌワシ木材」。しかし、長年手入れされてこなかった山の人工林は、木の曲がりやねじれが多く、板材として使える部分が限られています。
さらに、険しい地形や厳しい気候の影響もあり、木材を運び出すだけでも大きな費用がかかります。
活用には想像以上の手間とコストがかかるため、持続的な活動にするのは厳しいと考えられていたと語る森本さん。でも今、少しずつ社会の共感を得ながら着々と前に進んでいるそうです。
森本さん:この地域で30年以上にわたってイヌワシの観察やモニタリングを続けてきたという背景を踏まえて、企業の方々に「この木材は、森林の再生や生物多様性の象徴としてのイヌワシの保全につながる」「気候変動対策の視点からも意義がある」とお話しをさせていただきました。
−−気候変動の対策というのはどういうことでしょうか?
森本さん:木は育っているあいだ、大気中のCO2をどんどん吸って、炭素を体の中にためていくんです。でも、ある程度大きくなると成長が止まって、吸収の力もだんだん弱くなっていきます。そして、やがて枯れたり倒れたりすると、木の中に溜め込んでいた炭素が徐々に空気中に戻ってしまいます。
そこで、元気なうちに木を切って、それを家具や建材などに使えば、炭素は“木の中”にとどまりつづける“炭素の固定”ができるんです。

森本さん:また、木を切ったあとにできたスペースには、また新しい木が育っていきますよね。するとその新しい木が、またCO2を吸収して、炭素を閉じこめるというサイクルがおきます。成長の遅い自然林は、10年程度では人工林を伐採せずに放置するよりも木々に蓄えられるCO2が少ないのですが、100年以上かけて豊かな自然林に復元すれば、人工林と同等以上のCO2を蓄えられることを明らかにしました。
−−そうした循環が起きていることは知りませんでした。企業でも「なるほど!」と関心する方が多そうですね!
森本さん:そうですね、この取組を5年間支援してくださったHSBCという海外の金融機関は、「ネイチャーポジティブ(NP)」や「ネイチャーベースドソリューションズ(NbS)」といった国際的なキーワードとも重なるということで、実際に資金を提供してくださいました。
私達の活動が、ローカルな現場で、国際的に議論されていることを体現している、そんなプロジェクトだと捉えていただけたのだと思います。もちろん、取り組み当初は「一体いくらかかるのか」というのも想像できず、正直資金面からみると、厳しいのは目に見えていました。
でも、実際に「まずはやってみよう」と様々な形で、トライヤルを重ねていく中で、具体的なコストが見えてきましたし、その試算をもとに、茶屋さんとも相談しながら価格設定や今後の展開についても考えていくことができました。
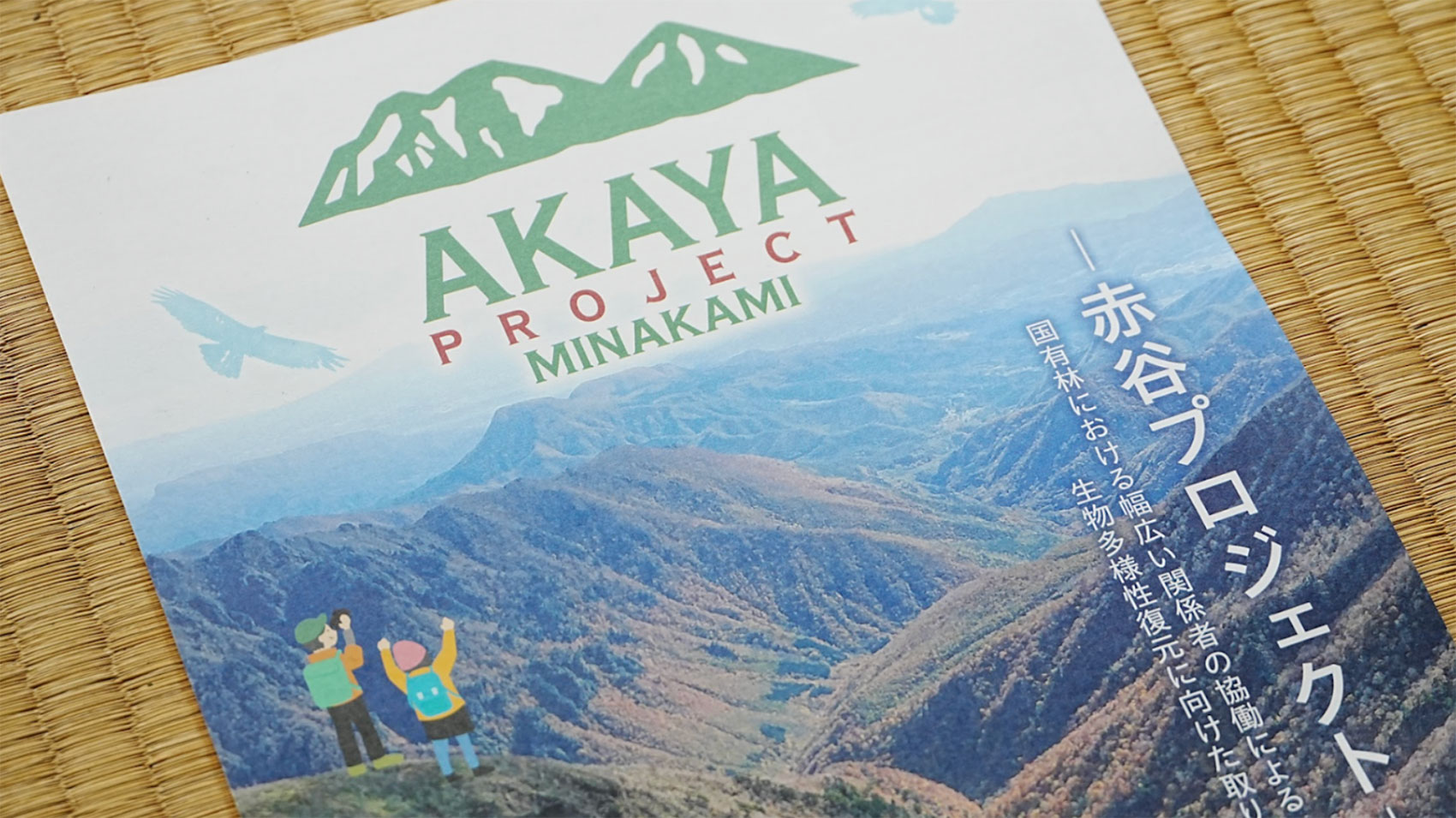
小さな気づきが、未来をひらく
−−これからも継続してこの取り組みや森のことを未来につなげていくには、やはりこれからを担う子どもたちへ伝えていくということも、とても大事になりますね。本日はたくさんお話しを伺いましたが、最後にこの活動を今後どう取り組んでいきたいかなど、教えてください。
森本さん:これからも引き続き子どもたちには伝えていきたいですね。
ありがたいことに、この町の小学校はすごく関心を持ってくれているんです!私たちが学校にうかがって自然の話をすることもありますが、授業の一環で“探究学習”として森に入り、実際に自然にふれる時間を持ってくれています。
みなかみ町の子どもたちはセンスが良いですね。最初は不慣れで嫌がっていても、森に入ればすぐに虫を捕まえたり、鳥の羽を拾ったり、見つけたものに「これなに?」「どうしてこうなってるの?」と、どんどん質問してくれるので、自然に対する“目”や“感覚”がとてもいいなと感じます。
大人も含めて「危ない」など先入観で自然を遠ざけてしまうのは、やっぱりもったいないと思うんですよね。大事なのは、知識よりも“体験の機会があるかどうか”だと思うんです。
この赤谷の森は、そんなキッカケを届けられる場所でもあると思っています。地域の子どもたちだけでなく、都市部の子どもも含めて、できるだけたくさん自然にふれて、よく見つめ、科学的に考えながら、実際にアクションを起こす体験をしてほしいと思いますね。
−−体験を通して自然に気づきや好奇心が芽生えて学びにつながることも多いですよね!やはりここでも伝えていくということが大事になりますね!

森本さん:はい、私たち日本自然保護協会のような団体が、自然を守ろうと言っても、実際にはどうしても身構えられてしまうことが正直多いんです。
でも、茶屋さんもおっしゃったように『イヌワシストア』のような場所から、自然にキッカケが生まれて、もっと深く知りたい人は自分から調べてくれるようになると思います。
大事なのは、“目指す山の頂”をみんなで共有しながらも、そこへ向かう“登山道”は人それぞれだということ。
そして、役割分担も多様で、私にしかできないこと、茶屋さんにしかできないことがある。でも、目指している景色は同じ。そんな関係でありながら、お互いが補い合って進めて行けたらと思っています!
−−茶屋さんはいかがですか?
茶屋さん:そうですね、先ほどもお伝えしたように正直、理念とか大義より、いかに本質を伝えて、行動していくかが大事だと思うんです。
森本さんは、その部分を伝える立場としてすごく大切にしているし、実際に行動していますよね。大義を語る人は多いけど、それを実現するために動き続ける人は本当にわずかだと僕は思います。
だから、自然が大事。環境が大事。そう言うのは簡単だけど、実際に泥まみれで手を動かしてる人たちがいるということも、やっぱり知ってもらいつつ、その積み上げがあって初めて、言葉にも意味が生まれるんじゃないかなって思います。
繰り返しになってしまいますが、引き続き僕は僕の役割をやれる範囲の中で最大限やっていきたいと思いますね。
−−補い合って前へ進んでいくということをそれぞれの立場で体現されていくのが、すごくイメージがつきますね!本当に本日はありがとうございました!
小さなキッカケが、誰かの心を動かし、行動へとつながっていく。イヌワシストアが担うのは、そんな“つなぐ場”としての静かな役割でした。
そして「赤谷プロジェクト」がこれまで続けてきた“イヌワシや森を守り育てる”という活動や想いは、人から人へと受け継がれ、確かな未来に向けて進んでいます。
-infomation-
イヌワシストア
イヌワシ木材について
Instagram
日本自然保護協会













