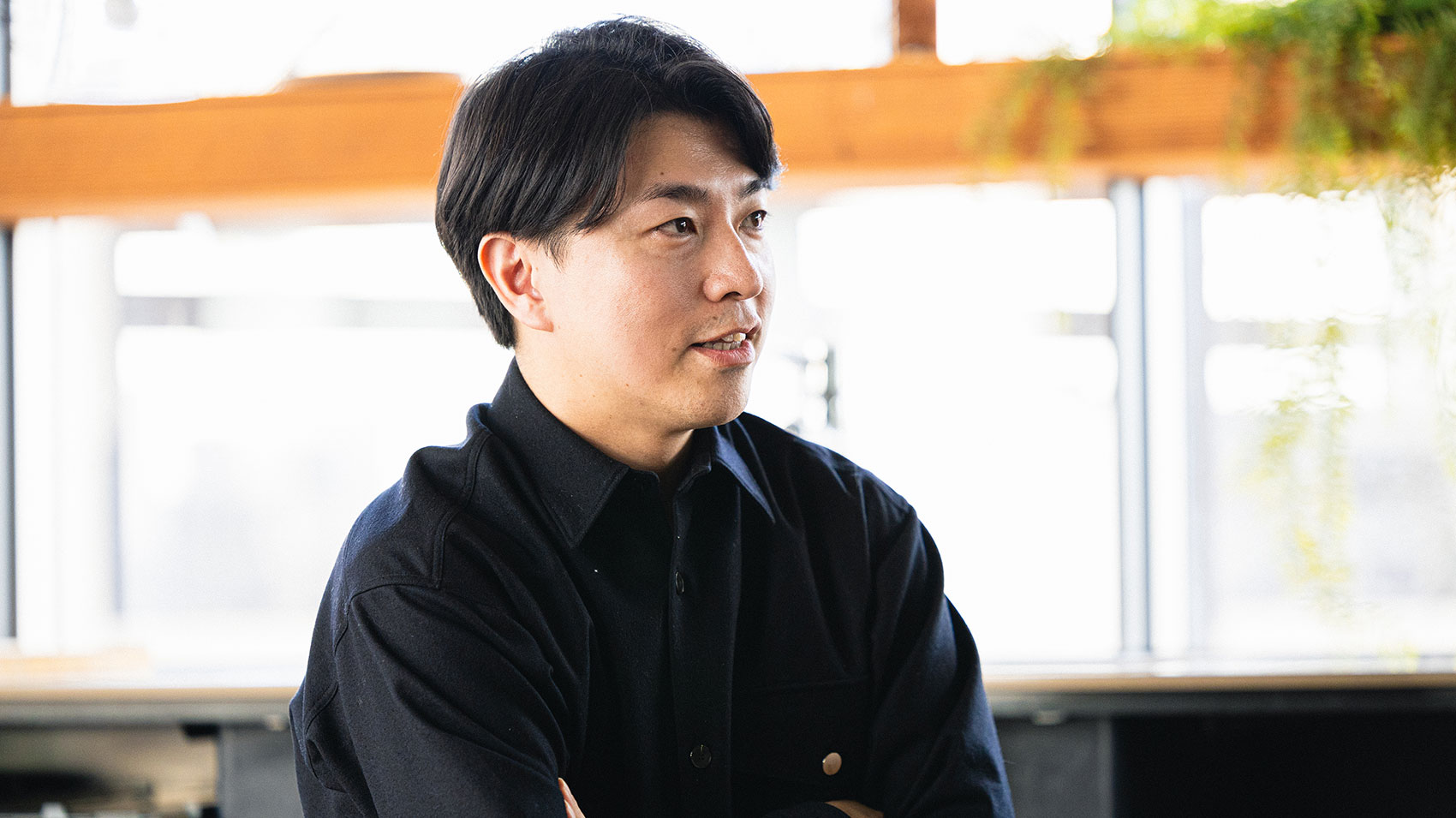
本当の価値を食を通して届ける
それがMo:takeの役割
大垣:今日は初めて坂本さんと対談するということで少々緊張もしていますが、改めてMo:takeのこと、Mo:take MAGAZINEへの想いなどを振り返りながら、これから始まる新しい音声メディア『Mo:take VOICE』についてのお話しもしていければと思います!宜しくお願いします。
坂本:普段はよく編集会議などでもしっかり話しているけど、こうして改まって対談ってかたちでお話しするのは、意外に初めてですよね!まぁ緊張せず、いつも通りでいきましょう!宜しくお願いします!
大垣:そうですね!自分たちらしく!というわけで、早速ですがMo:take MAGAZINEについて、どんな想いで携わっているのか、僕からお話ししてもいいですか(笑)!?
坂本:おっ!早速ですね、どうぞどうぞ(笑)!
大垣:僕はMo:take MAGAZINEに関わらせてもらって、改めてMAGAZINEは色々チャレンジさせてもらえる場だなぁって思ってるんです!
ご一緒する前まで、商品やサービス、企業のことを知ってもらうための広報活動をサポートするPR会社にいて、主に、TVや新聞、雑誌、WEBメディア、ラジオといったメディアの方々に情報を届けて、そうしたメディアで放送されたり記事になることで、世の中に知ってもらうための活動をしていました。様々な情報を扱いながら刺激や学びもあった一方で、もっとクライアントに寄り添ってできることはないか、本質的な広報やPRってなんだろうって悩むこともありました。
そうしてこれまでメディアの方々を中心に情報を届けていた自分が、今はメディアを運営する立場になって、その“本質的な人の想いを聞いて、記事としてお届けできること”はすごく新鮮なんですよね。

大垣:今は、どんなコミュニケーションでその人の本質を聞くことができるのか、様々なコミュニケーションのあり方や取材環境などを考え、工夫しながら取材をしています。これも自分にとって新しい挑戦です。
こうした挑戦ができるのも、Mo:take MAGAZINEに携わり出した当初から、Mo:takeについての理解を深めるための時間をかなりとって、坂本さんが丁寧に説明してくれたことや、坂本さんとだいぶ壁打ちをさせていただいたことが、大きいですね!
その中でよく出てきた坂本さんの「食はメディア」という考えが斬新で衝撃的でした!
坂本:そうですね!Mo:take MAGAZINEに携わってもらう時、まず最初にMo:takeの役割や概念をどう捉えるかということがすごく大事だと思ったので、はじめに結構お話しましたよね。
Mo:takeはケータリングサービスやフード開発、プロデュースをしているっていうイメージが目立つので、そのイメージだけでMo:take MAGAZINEに関わると、恐らく食べ物に特化した「食関連のメディア」になってしまうと思ったので、はじめにMo:takeというブランドの想いや、考え方、そして、概念をお伝えしたんです。
Mo:takeというのは「食を起点にした体験や、その楽しさを伝える」という概念を大事にしているブランドなので、ものごとの“本当の価値を食を通して届ける”というイメージをもっています。そういう意味でも「食はメディア」だと思ってるんですよね!

ケータリング事業からも垣間見えるMo:takeスピリット
大垣:Mo:take MAGAZINEに携わり出した当時は、そんな風に考えたことがなかったので本当に「目から鱗」でした。でも、その話をMo:take MAGAZINE目線で深ぼっていくと、「食べ物」に限定しない「食」に関わるヒト・モノ・コトが見えてくるんですよね。例えば、料理人だけでなく食に関わる場を作る人、「食」に関わる道具などのモノ、「食」を切り口にしたイベントなどのコト、というように色んな切り口で考えられるんです。
取材したいと思うヒト、コト、モノにおいて記事の中で知らせるべき背景のストーリーの必然性が見えてきたり、無限の可能性を感じたのを覚えています!
そして、坂本さんはMo:takeのケータリングも“オフラインメディア”と捉えていますよね!
坂本:ケータリングは特に食べるという行為が伴うので、以前から何かを知るキッカケを作りやすいと思っていたんですよね。
例えば、イベントなどにはコンセプトや目的がありますよね?
Mo:takeケータリングは、そのコンセプトや目的に合った食体験を提供しています!その部分をフィットさせることで、イベントの参加だけではもしかしたら伝わらない部分を、食体験を通して、伝えるきっかけになるかもしれないって思ったりもしますね!
大垣:そうですよね!そしてケータリングによる場のデザインと言いましょうか、視覚体験としても、すごく華やかで印象的なものも多いですよね!
しかも、必ずしもイメージが固まってオーダーされるわけではない。例えば、色の指定だったり、「ジャングル」がコンセプトだったり、 そうしたザクっとしたイメージをMo:takeらしく形にできるのが面白いし、すごいと思います!
そのセンスが羨ましいとさえ思います(笑)!
坂本:いえいえ!センスというよりは、お客さまが考えていることをどれだけキャッチアップできるかなというのが重要な気がしますね。
例えば「ジャングル」がテーマなら、そこに至るまでの経緯や想いを聞き、そこから依頼者が考えるイメージを考えて、「それってこういうことですか?」と言語化しながら共感し、方向性を決めていきます。
ただ僕の中では料理面ではもちろん“美味しさ”なんですが、食体験としての“楽しさ”という視点をすごく重要視した結果のデザインだったりするので、絶対にこれはこうする!というパターン化したような強いこだわりはそこまでないんです。
周りからこだわり強そうに見られるんですけどね(笑)。

他のメディアと同じじゃ意味がない。Mo:take MAGAZINEのコンセプトは“B面”
大垣:やっぱりMo:take自体がこだわりに縛られずに「本当の目的」のためにやっているんですね!MAGAZINEのコンテンツを作るうえでもそうした考えのもと議論することもありますが、“こうでなければいけない”というこだわりに縛られないのは、僕としてはありがたいです(笑)!
だからこそ、Mo:take MAGAZINEも色々な挑戦ができるメディアになっていけるんだと思います。僕が参画した時点でいろんな記事があって、どれも違う角度から取材されていてバラエティに富んでいました。
Mo:takeも進化し続けるなかで、これからMo:take MAGAZINEもどう進化させていこうかと話した結果、坂本さんの芯にある「楽しさと新たな発見を伝える」部分と、僕個人が大切にしている「人の想いをちゃんと届ける」部分を掛け合わせて、より色濃く打ち出せるのではないかと思いました。
そして現在では、取材を受けてくれる方が話しやすいような空気作りや、生の声を吸い上げられるように雑談ベースで話すなど、形式的なQ&Aとは違うアプローチでの取材を中心にしています!
そうすることで、他のメディアではまだ語ったことがない情報も引き出しやすかったりするので、そこを取り上げることを意識しつつ、丁寧な取材を心がけてます! まさに毎回チャレンジでもありますが、それを楽しんでますね!
坂本:雑談ベースで話して、取材を受けてくれた人の“本質”の部分、その人の内にある情熱を記事で表現したいですし、そうすることでその人の本当の魅力を広く伝えるお手伝いができればいいと思っているんです!
取材で一番面白いなと思うところは、取材を受けた方から“取材を通して自分の新たな気づきを得ました”って言葉をもらえることが多いかなって思うんです!
大垣:ありますよね!「あぁ!今聞かれて初めて自分がこう考えてたんだってわかりました」みたいな瞬間!あれは僕としても嬉しい瞬間です!
坂本:そうそう!取材の中で、幼少期まで遡って話を聞いて、「そういう子どもだったから、今こういう風に考えるようになったんですか?」と聞くと、「あ、確かにそうかも」ってなるんですよ。そこはメディアとして大切にしていきたい部分でもありますね。

大垣:あと「食」がテーマだから「食」を起点に掘り下げていくんですけど、結構いろんなエピソードが出てくるんですよね!取材を受けてくれた方の原体験が今の仕事のスキームや現在の思考回路につながっているんだなと、思うこともよくあります。
そうした部分や想いや考え方、その人が得意とする専門分野などのお話も、出来るだけわかりやすく、そして興味を持ってもらえるように読者へ伝え、その人のキャラクターや現場の臨場感届けるために、記事ではカジュアルに表現しているのも重要な部分だと思います!
ちなみに坂本さんは、メディアの人でもないのに、話を掘り下げて聞くという視点をもっていますよね?
坂本:僕が掘り下げる理由はすごくシンプルで、“ちゃんとその人の言葉を届けたい”という気持ちだけなんですよね。
あと、これまでその人やコトの“本質的なB面”を掘り下げて届けているメディアが少なくて、自分が知りたいから質問したくなるという感じもありますね。
だから、大垣さんも言ったように他で掲載しているような話ばかりの記事は掲載したくないんですよね!
それよりも、「どうしてやろうと考えたの?」「本当は良いことばかりじゃないよね?」みたいに踏み込んだ質問をして引き出すという、本音の部分を教えてくださいというスタンスですね。
大垣:そうですね!“B面を掘り下げて届ける。”
まさにそれがMo:take MAGAZINEのコンセプトかなっていうのも共通の認識としてありますね!だから、記事の構成を考えるときもこだわります。他の媒体で掲載されている記事がある場合はその記事を読んでから、「この部分をもう少し掘り下げてみたい」という部分にフォーカスして組み立てていきます。
坂本:そうそう!取材前から取材後、記事制作、公開前まで大垣さんと結構やりとりしますよね!
大垣:はい!そのおかげで記事に対する固定観念が壊れました。特に文字数とのバランスで削りたいこともあるんですが、「いや、ここは伝えたいから削るのは止めましょう」ということが多々ありますもんね!
坂本:うん、文字数にこだわるよりも伝えたいことを伝えたほうが絶対にいいし、結果として、そのほうが取材を受けてくれた人のためにもなることの方が多いのかなって思いますよね!
大垣:そうなんですよ!嬉しかったのは、文字数は多くなったんですけど、記事の内容が濃いということで、ご自身のプロフィール代わりに記事を活用される方もいらっしゃって!
記事が別の形で役に立ったり、取材を受けてくれた人が喜んでくれるのはすごく嬉しいです!
だからこそ、このコンテンツを広く知らせて、知ってもらうキッカケをつくることも僕たちの課題であり、役割の一つかなって思います!

生産者のリアルから人との関わり方まで。「食」起点で幅広く語れるのがMo:take MAGAZINEの持ち味
大垣:本当にキッカケを作りやすいというのを感じますね!
先ほど少しお話ししましたが、Mo:take MAGAZINEに携わるようになって、「食」ってすごく幅広いんだなと実感しています。
例えば、料理人を取材する場合、料理の話やこだわりポイントを聞くだけじゃ終わらないんですよね。どんな思いで料理を提供しているのか、なぜ料理の器はこれにしたのか、そこから話が広がって器を作った人はどんな人なのか。
フォーカスする対象を広げられるし、いろんなコミュニケーションのキッカケを作れる!「食」でここまでできるんだと知ったのはMo:take MAGAZINEに携わったからでした。
ちなみに、坂本さんがこれまでを振り返ってすごく印象的だったり、忘れられないエピソードはありますか?
坂本:色々ありますが、今まで農家さんをはじめ、林業や漁業の方々といった生産者さんの話を色々と聞いてきたけど、それぞれの目線でのリアルな話は気づかされることがすごく多いですよね。円安や世界情勢などの影響で輸入品を中心に価格が高騰しているけど、例えば、農家さんには関係なさそうと思いきや、実は日本の農業は輸入した肥料に頼っている部分も多いから打撃が大きいとか。漁師さんから魚の漁獲量が減っていると聞いて、じゃあ僕らはこれから何をするべきなのか?と考えたり。
社会問題だけでなく、生産者さんのお客さまに対する想いを聞けるのも個人的には感慨深いかなと思っています。
それと何よりも、お客さまのためにどういう気持ちで取り組んで、生産しているのかなどを聞いたときは、感銘を受けますね!
大垣:そうですね。また生産者さんの畑など、現場でお話を聞くこともあるじゃないですか?
例えば農家さんの取材では、取材時に、収穫体験をさせていただきましたが今まで農業経験のない自分にとっては体験と情報が伴って本当に視野が広がったし、意識することも増えました。
例えばスーパーに並んでいる食材から生産者さんのこと、その背景について意識するようになったのは、自分でも変化を感じますね。

Mo:take VOICEに込めた想い。
大垣:ここまでMo:takeのこと、Mo:take MAGAZINEのことを話してきて、改めてこれから始まるMo:take VOICEの役割や可能性も感じてきましたよね。
Mo:takeとして、オンラインメディアのMAGAZINEがあって、オフラインメディアのケータリングや食のコンテンツがあり、そして“記事の裏側にあるストーリーを届ける”Mo:take VOICEが誕生!
坂本さんは、Mo:take VOICEはどんな役割になると思いますか?
坂本:ケータリングやMAGAZINE、商品開発やプロデュースで今までどうしても伝えきれないことを、伝えやすくするのがMo:take VOICEの役割になって、今までとは違う表現方法となる音声で届けるというのが一番の特徴ですよね。
それにVOICEにしかできないこと、VOICEだからこそ伝えやすくなったこと。この2軸ができたように思いますね!
大垣:すごくわかります、その場の臨場感や興奮度合いを伝えてることで、より肉厚な情報になるというか、僕らなりの取材のスタイルで抽出されるその人の言葉や、文字では起こしきれないその人の感情が伴ったメッセージ、その人の声で届けられるリアル感をお届けできるのは嬉しいですね!
僕は、その人自身が話すからこそ言葉には想いや感情が宿ると思っているんですけど、それを文字にしてしまうとサラッと流れてしまうことがあるんですよ。

坂本:そうですね!だからこそ、直接話している温度感をそのままに、音として伝えるVOICEの役割って本質を届ける上では重要だと思います!
MAGAZINEもVOICEもそれぞれコンテンツとして成立しているけど、お互いを補完し合う。そんな関係性になって、さらにお互いの特性を活かした相乗効果で、より充実したものをお届けできると思っています!
あとは、取材中に「あの話すごく刺さったよね」ってことを取材の後に2人で良く話したりするじゃないですか、取材現場だからこそ感じることや、少し話が外れたりして記事には起せないけど、裏エピソード的な話。そういった編集部だからこそ語れる取材の裏側などもお届けできるのも面白いですよね!
大垣:本当にそれ、ありますよね!取材中、いつも熱いお話が胸に響きまくってしまうのでかなりエネルギーを使うんですけど、取材後2人で話して共感ポイントをシェアし合ってますよね(笑)!そんな共感ポイントを大垣視点の「声」でもお届けして、 読者やリスナーに登場するゲストの方の想いをこれまで以上に分厚く届けられればと思いますね。
坂本:生の声を届けるという意味でも、生産者さんや多様な業種の方で座談会をするのも良さそうですし、飲食店や生産者さんの畑や製造現場の音とともに声を届けるとかも面白そうですよね(笑)!

柔軟な発想でリアルを届ける!
Mo:takeのこれから
大垣:そうですね!座談会や現場から声を届けるのもいいですね!やってみたいです!
そしてもう一つ、VOICEではMo:take MAGAZINEの取材を受けてくれた方だけでなく、VOICEだけに出演いただいて声を届けられる場にもしていきたいんですよね!
そうすることで、その先に新たな仲間ができるんじゃないかと思っています!
坂本:そうですね、恐らくVOICEは僕たちが今構想している以上に展開の可能性があるコンテンツだと思っているので、僕自身もアンテナを立てて、新しい使い方を見つけられればと思いますね。MAGAZINEでもケータリングでも、商品開発やプロデュースでも、いろんな展開ができるように進めていきたいですよね!
例えばMAGAZINEでは、取材対象の方をリサーチしていく中で、新しい出会いにつながったこともありましたよね!
ケータリングや商品開発そしてプロデュースの中でも、ヒトやコトに対する想いやストーリーがつまっているので、そうした現場にもマイク一つで、来てもらうとかね!
大垣:確かに、ケータリング、商品開発やプロデュースまで広げれば、VOICEは縦横無尽に活用できそうですね!
そうした現場で、どんな方がどんな思いで、何を届けたいのか、どうしてそういったオーダーをしたのか、Mo:takeとしてどんな想いでクリエイティブしたのかなど、こうした声を届けていくという使命も感じました!
これから先、Mo:takeブランドと一緒に、MAGAZINE、VOICEも両輪で育てていきたいですね!
単なる「食」の情報発信ではなく、食に関わる人の想いやストーリーを深く掘り下げ、リアルな想いを伝えてきたMo:take MAGAZINE。
その背景にあるのは、「食を通じた体験の楽しさを伝えたい」「その人やコトの本質に迫りたい」という強い想い。そして新たにはじまるMo:take VOICEでは、取材の裏側のストーリーを声でお届けしていきます。
これからも、柔軟な発想で「食」を軸に新たな表現を生み出していくMo:take。その進化にもぜひご注目ください!
– Information –













