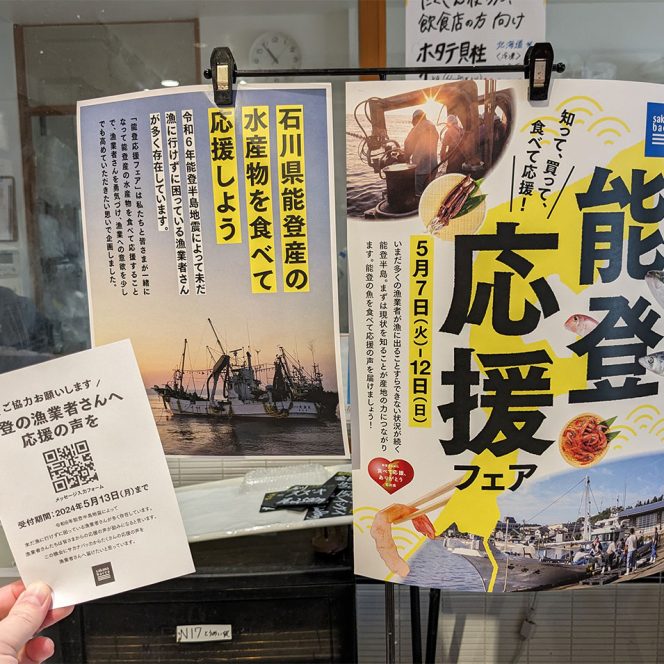企業努力とは、種をまき続けること。
−−これまで木下さんの足跡や会社への想いなどを伺ってきましたが、実際ごま油の製造をされている方は何名くらいいらっしゃるんですか?
木下さん:6名ほどですね。一番若い人で20代、現場責任者は40代の人に任せています。
−−新しい世代の方が、技術を受け継ぎたいという想いを持って来てくれるのは、嬉しいことですね!
木下さん:もちろん、これからも製油所を続けていくために、担い手になってくれる人がいるのは嬉しいですね。一方で、労働環境については改善していかなければいけないところもあります。
近年は夏の暑さひとつとっても、一昔前の暑さとはまるで違っていて、猛暑日も多く、長くなっていますよね。設備を簡単に移動したり、止めるわけにもいかないので、気候の変化に合わせて労働環境も変えていかなければならないという課題はありますね。
−−木下さんはこれまで、自ら広報戦略を立て、PRを手がけてこられました。その取り組みが記事として紹介され、それを見た方から声がかかったり、「SOSOGE FES2024」のようなイベントにも参加されていますよね。そうした積極的な姿勢は、次世代を担う若い従業員の皆さんにも、引き継いでいこうとされているのでしょうか?
木下さん:その点については、ときどき私も従業員に、「とにかく種をまき続けるしかないよ」と言っています。
まずは種をまき続けること
私はそれが企業努力だと思っているんです。
その種が、いつ、どこで、どのように芽が出て花開くかは、蒔いた量やタイミングによって変わってくると思います。1ヶ月後かもしれないし、半年後、あるいは5年後かもしれない。でも、いつか「あの時まいた種が、今こうして実を結んだんだな」って収穫できる時がくるかもしれませんよね。「だから種を蒔き続けるんだよ」と従業員に伝えています。

授業を通じて高校生に伝えたいのは、モノの裏側にあるストーリー。
−−地域への広がりという点で、学校の授業の一環で、企業訪問先として受け入れをされているとのことですが、もともと「村松製油所」では、学校や地域とのつながりを積極的に持たれていたのでしょうか?
木下さん:それは私が経営者になってから取り組んできたことです。今思い返せば、レストランをはじめようとした時と一緒で、私が“浜松産のごまを作りたい”という一方で、現在連携している地元の高校では「企業と授業をしたい」と、ここでまた想いが合致して「浜松で胡麻を育てる授業」を取り組むこととなりました。
−−具体的にどんな授業をされているんですか?
木下さん:高校生と畑に行って先ずは土づくりから耕し、水分の保持や病害虫の予防のために、土の表面をシートで覆います(マルチング)。そして、ごまの種を蒔いて、芽が出てこなければ、再度、種を蒔いて、雑草を抜きます。そこに花が咲いて、種ができ、その種をごまとして収穫するといったところまで活動をします。
−−高校生は実際に畑作業も体験するんですね!授業のテーマは何だったのですか?
木下さん:授業のテーマについては、実はすごく大きな構想を持っているんですよ!物事には何事にも裏側があります。例えば、コンビニエンスストアに行くと、ペンが普通に売っていて、それを消費者が買います。それは当たり前の光景であって、何不自由なく、私たちは便利にモノを得ることができます。
でも、その背景には、商品を売ってくれる販売店、納品してくれる配達員、それを仕分けしてくれる人、もっというとその商品を作ってくれている人がいますよね。
そういうたくさんの人が関わりながら、モノができているんだよってことを、授業を通じて知ってもらいたいと思っています。

−−この授業を通して、自分の手に商品が届くまでのプロセスや、人との関わりや構造を体験を通して学べるということですね。
木下さん:そうですね。うちの場合、ごまを調達して圧搾して、ボトリングすればごま油ができますが、実はごま油の原料である「ごま」も誰かが作ってるんですよね。そしてそれは、土を耕すところから始まるわけです。石を取って、畝を立てて、種をまいて、雑草を取っていくなど、様々な段階を経て、初めてごまができるんだということを、体験してほしいと思っています。
−−確かに、モノがどのようにして、どのような人によって作られているのかを理解するのは大切なことですね。
木下さん:彼らは高校を卒業して、すぐに進学する人もいれば、社会に出る人もいます。さまざまな選択肢がある中で、社会との接点というものを、少しでも早く、なんとなくでもいいから感じてほしいなと考えています。その想いを先生とお話して、この授業を実現させていただきました。
授業は1年間のプログラムで、最後には、収穫したごまをみんなで料理して食べるところまでが、1つのストーリーになっています。高校生と料理実習をやって、ごまをふんだんに使った料理を作ってもらおうと思っています!
−−いいですね!これまでMo:take MAGAZINEで農家さんなどの取材もさせていただく中、特に都市の子どもたちは土に触れる機会が少ないというお話しも良く耳にします。今後は県外から要望があった場合にも受け入れる可能性はありますか?
木下さん:そうですね!もちろんこのプログラムが1つの形にできれば、県外にも拡大していきたいなと思っています!

5千年の歴史を誇る「ごま」をもっと知ってほしい。
−−木下さんは、様々な取り組みを通してごま油を知るきっかけを作ってこられたと思いますが、木下さんから見たごま油の魅力についても聞かせてください。
木下さん:私はごまって本当にすごいものだと思っているんです。ごまの歴史は5千年もあり、ごま自体を知らないという人はほとんどいないんじゃないかと思っています。でも、ごまがどうやって育つのか、ましてや日本で消費されるごまのうち、国産のごまは1%未満しかないという事実も知られていないですよね?
ごまの粒ってすごく小さいんですが、それが五千年も、ずっと淘汰されずに生き続けてきているんだから、やっぱりごまのパワーはすごいものなんだと、私は信じています!
ごま油の歴史を少し紐解いてみても、オリーブとごまが最古の油と言われているんです。これまで、色々な油が出てきては消えてきた中でもごまが、ずっと深く長く人々の生活に存在し続けているっていうことは、それだけごまにすごいパワーが秘められている証だと思います。そのことを、もっと皆さんに知ってもらいたいなと思います!
また、現在国産のごまが少ないのが現状ですが、私自身も浜松産のごまをもっと増やしていきたいと考えています!

「浜松一」の油屋を目指して
−−最後に木下さんが会社を継いでから7年経ち、今、思い描いている「村松製油所」の未来をお聞かせいただきたいです!
木下さん:まずはこの『村松製油所』をしっかりと維持していき、次の100年にも会社が残り、その先も続いていくようにしたいという想いがあります。
加えて、現在は、「浜松唯一の油屋」だと言っていますが、“浜松に唯一1軒しかない油屋”の「唯」を抜いて「浜松一の油屋」にしたい、それが私の野望です!
そして、“浜松といえばごま油”だと思っていただけるように、地元にしっかり根を張った油屋を目指しています。
−−いいですね!これまで木下さんを支えてこられた奥様としても、『村松製油所』がこんな場所になってくれたらいいな、という想いはありますか?
奥様:そうですね、ちょっといい油だけど、親しみのある地元の油屋さんになれたらいいなと思います。だから、イベントや祭りなど、周りの人と一緒に何かをするっていうことを大事にしていきたいですね。
ここには常連のお客さんが、お友達を連れてきてくれるんですが、その時はもう私の説明がいらないぐらい、全部その常連さんが商品の説明をしてくれるんですよ!
こういう方が、またお客さんを呼んできてくださっているんだということをすごく感じます。ふらっと来て、ちょっと会話して帰ってくれるような、そういう場所になれたらいいですね。
−−木下さん、奥様、本当に素敵なお話しをありがとうございました!
19年間の安定したサラリーマン生活から、未経験の油屋経営へと転身した木下さん。「会社を継ぐというのは、生半可なものではない」という言葉が、今も心に残っています。その言葉には、伝統を受け継ぐことへの深い葛藤と、強い覚悟が込められているように思います。
経営者就任後は、仲間である社員の結束力を高めるために取り組んだことや、コロナ禍という危機に直面しながらも、常に新しいアイデアと行動力で道を切り拓いてきた木下さん。「種を蒔きつづけることが企業努力」と語るその姿勢こそが、これからの100年に続いていく。
「浜松一の油屋になりたい」
その木下さんの野望が現実のものとなる未来がきっと訪れると信じて、編集部はこれからも『村松製油所』に注目していきたいと思います!
– Information –
『村松製油所』
所在地 :静岡県浜松市中央区湖東町4176
営業時間:10:30~16:30
定休日 :月曜日